「言葉にできない」は「考えていない」のと同じ。
SNSを使うのが当たり前の今の時代、
ラインやメッセージ、文字だけでは気持ちを表現できず、ニュアンスを
伝えるのが難しい。
会話でいえば、仕事やプライベートで、自分の言いたいことが言葉にならない。
相手に思いが届かない、理解されない、会話が続かない。
などといったことが少なからずみんなあると思う。
そこで、本書では急激に言葉を磨くことはできないが、
「内なる言葉で思考を深め、外に向かう言葉に変換する」といった流れを体得
することで、一生モノの「言葉にできる力」を手にすることができる本。
本記事では「言葉にできるは武器になる」の要約、解説をしていきます。
内なる言葉
内なる言葉とは
・物事を考えたり、感じたりする時に、無意識のうちに頭の中で発している言葉。
外に向かう言葉
・一般的に言葉と呼ばれているもので、相手と意思疎通を行う道具。
本書でカギとなっているのは「内なる言葉」の存在である。
内なる言葉を磨く
私たちは相手の言葉に対して、言葉を「重い、軽い」「深い、浅い」
といったことを感じることがあると思います。
言葉が「重い、軽い」「深い、浅い」というのは、自分の内なる言葉と向き合い考え、自らの思考をどれだけ広げ、掘り下げたかによって決まる。
対して、外に向かう言葉だけをどんなに鍛えたところで、言葉の巧みさを得ることはできるかもしれませんが、言葉の重さや深さを得ることはできません。
「内なる言葉」を磨くとは、内なる言葉で自分の中の意見を育てることでもあります。
自分の中の事を言葉にできてこそ、人の心に響く言葉を発することができる。
内なる言葉を磨く7つのステップ
2.「T字型思考法」で考えを進める
3.同じ仲間を分類する
4.足りない箇所に気付き、埋める
5.時間を置いて、きちんと寝かせる
6.真逆を考える
7.違う人の視点から考える
1.頭にあることを書き出す
頭の中のあらゆる考えを書き出すこと。
書き出すことで、自分が考えていることを把握することができるようになります。
単語でも、文章でも、頭の中に浮かんだことをどんどん書き出すことが大事です。
2.「T字型思考法」で考えを進める
ステップ1の頭にあることを書き出した内なる言葉について、
考えを深めたり、幅を広げたりします。
書き出した言葉に「なぜ?」「それで?」「本当に?」の3つの質問を問いかけて、
思考を進めていきます。
「T字型思考法」の詳しくは本書に書いてあります。
3.同じ仲間を分類する
ステップ1で書き出し、ステップ2で広げた考えを整理していきます。
分類の仕方は3つ。
①グルーピングする
②方向性を意識して順番に並べる
③グループに名前をつける
4.足りない箇所に気付き、埋める
ステップ3で分類した内なる言葉の考えをさらに広げたり、深めたりします。
このときにもし、内なる言葉が新たに出てきたならばさらに書き出します。
5.時間を置いて、きちんと寝かせる
この5ステップでは、何もしないこと。進めるのではなく一旦時間を置く。
常に一つの事ばかり考えていると、無意識のうちに考えが狭くなってしまったり、
冷静な目線を持つことができなくなることがあるからです。
6.真逆を考える
十分に寝かせた後は、ステップ4の「足りない箇所気づき、埋める」
一旦頭がリセットされているので、客観的にヌケモレに気づくことができる。
そして次のステップは真逆を考えること。
ここまでは自分の常識の範囲。
真逆を考えることは「自分の常識や先入観から抜け出す」ことにつながり、半ば強制的に別の世界へと考えを広げていくことになります。
真逆には3種類の考えがある。
例:できる⇔できない
2.意味としての真逆
例:希望⇔不安
3.人称としての真逆
例:味方⇔敵
7.違う人の視点から考える
あの人だったら、どう考えるだろうか?
違う人の立場になって、内なる言葉を違う視点から考えます。
他の人の立場になって考えると、考える幅をさらに広げられるようになるからです。
できるだけ具体的な人物を思い浮かべながら行うのが効果的です。
以上、ここまで「内なる言葉」を磨くステップを7つ紹介してきました。
やり方については簡単にポイントだけを書きましたので、詳しいやり方を知りたい人は本書を読んでいただきたいです。
自分という壁から、自分自身を開放する
物事の考え方は、その人によって大きく変わる。
あくまでも「自分の中では正しい」と思っている状態でしかないため、
自分以外の誰かの視点で考えることで、思考や考えの多様性を受け入れることが大事。
そのためにまず、自分が今「自分という壁」の中にいることを意識する。
この事実に気付かないでいると、無意識のうちに「自分が考えることは正しいに
決まっている」「自分が言っていることを、分からない方がおかしい」と
自分本位かつ排他的な感情を持ってしまう。
視野を広くし、視点を変えて、内なる言葉の語彙力も向上させていく。
まとめ
大切なのは、「内なる言葉」を磨いていく事。
「内なる言葉」を磨くこととは、内なる言葉で自分の意見を育てること。
自分の意見として言葉にできてこそ、人の心に響く言葉を発することができる。
外に向かう言葉だけでなく、内なる言葉に目を向ける。
それが、言葉を鍛えるためのルールである。
読んでいただきありがとうございます。
是非一度読んで見てください。
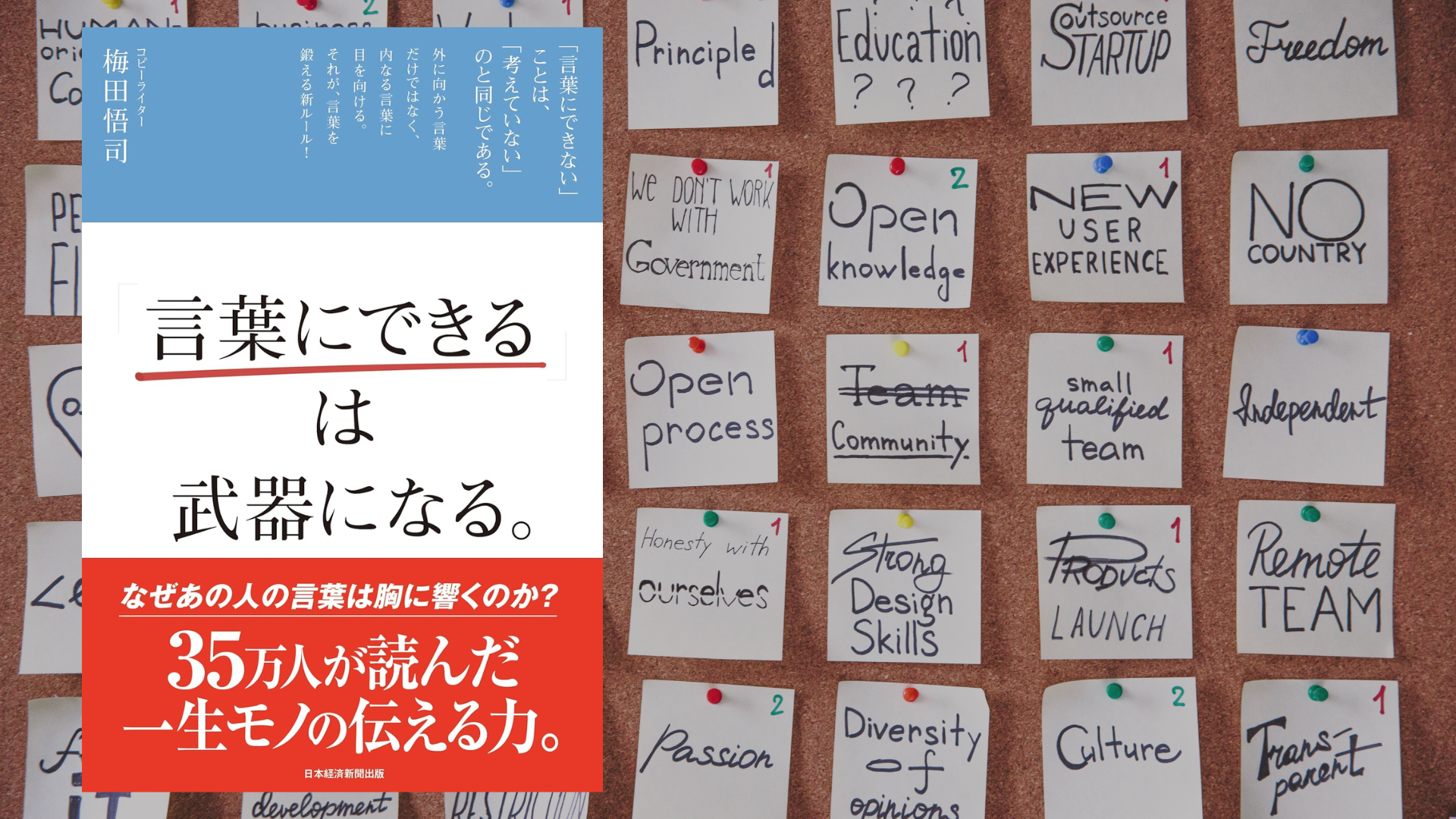


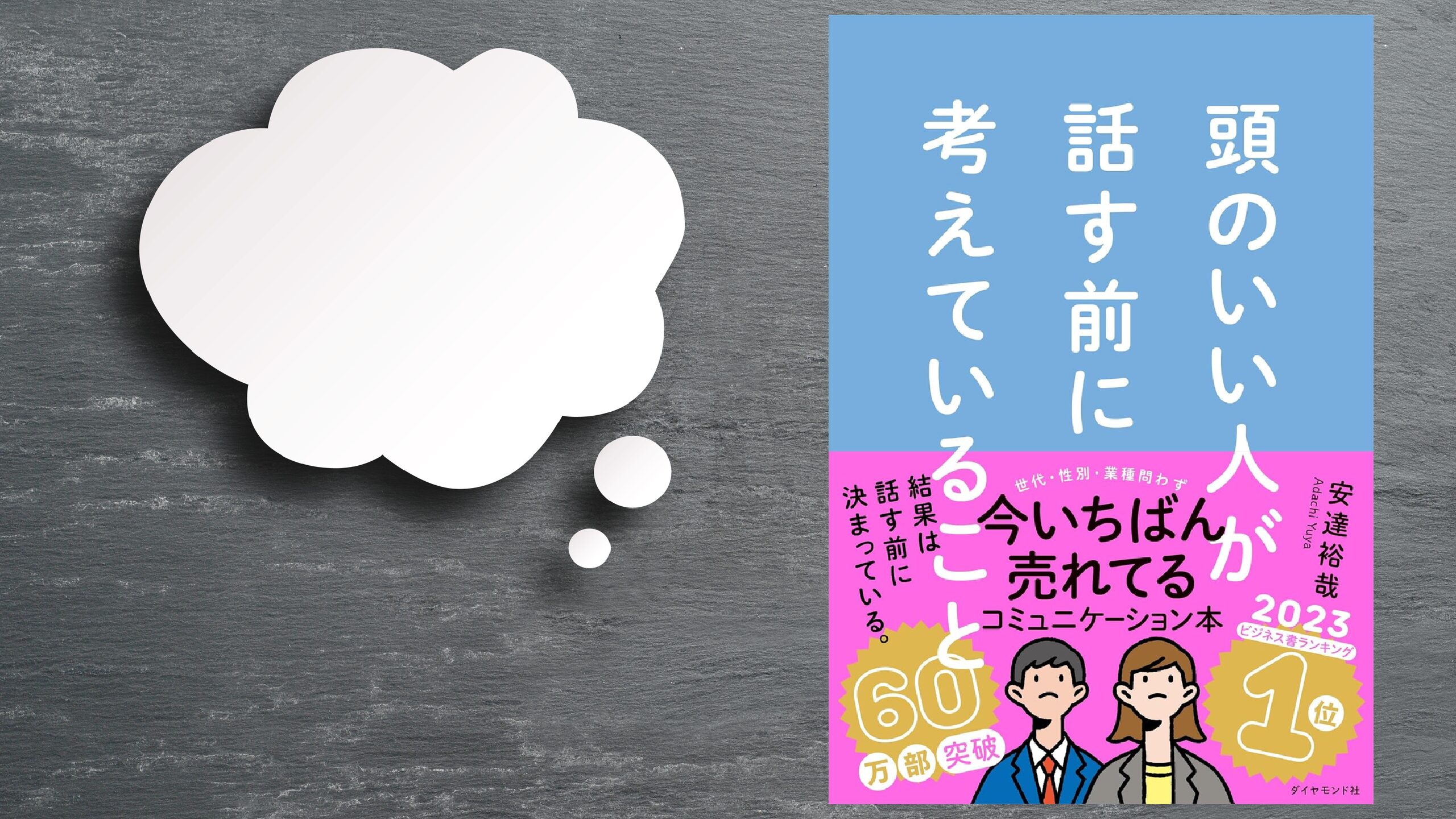
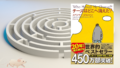

コメント