「どっちの服がいいと思う?」
デートで買い物中、こう聞かれたらあなたならどう答えますか?
知性と信頼を高める”7つのマインドセット”
頭のいい人が話す前に考えていることは何か?
そう答えは「話す前にちゃんと考える」ことです。
ちゃんと考えるとは何なのか、まず、心構え(マインドセット)の黄金法則を7つ、
その後、実践として有効な5つの思考法を紹介していきます。
1.とにかく反応するな
みなさんは「アウトレイジ」という映画は知っていますか?
アウトレイジは登場人物全員悪人のヤクザ映画です。
ひたすら殺人、暴力、理不尽が飛び交うたくさん人が死ぬ映画なのですが、
この映画で殺されてしまう人に同じ共通点があります。
それは、感情的な人です。感情的になった人が死に冷静な人が生き残る
感情的になった人はさんざん利用されたあげく、みんな殺されてしまうのです。
この映画で大切なことは、感情にまかせて反応するのではなく、冷静になること。
社会人はキレたら負け。一気に信頼を失くします。
すぐに口を開かない。スロー思考を起動する。
2.頭の良さは、他人が決める
頭の良さをIQや学力のことと考える人が多いのですが、
学歴がよかったり、IQが高くても必ずしも仕事ができるわけではない。
それでは「頭の良さとは」なんなのか?
・IQ(学校的知性)よりSQ(社会的知性)が重要
IQ(学校的知性)=偏差値、論理的思考、記憶力など数字やテストで測れるもの。
SQ(社会的知性)=数字やテストで測れないもの、他社の思考を読み、信頼を得て
他者を動かす力
社会で活躍する人は、社会的思考を身につけてから、学校的思考で復習していくように 学ぶ。この2つの思考を行ったり来たりして、思考をより深めていく。
論理的思考は立場も価値観も違う他人と考えを共有するために必要。
3.人はちゃんと考えてくれる人を信頼する
・賢いふりでは人の心を動かせない。
賢いふりとは?
「何か言っているようで、何も言っていない発言」「正論だけど中身がないアドバイス」等々。
・会議では最初に発言せよ。
最初に案を出す人は偉い。批判なんて誰でもできる。最初に案を出すのは勇気もいるし、勉強も必要だから、最初に案を出す人を尊重するべき。
最初に発言する人はもっと評価されてもいいのです。
相手のことをちゃんと考えていることは、言葉だけでなく、仕草や語調、態度で相手に伝わる。
4.人と闘うな課題と闘え
最近テレビや動画などの影響で論破しようとする人
・頭のいい人は論破しない
議論の勝ち負けではなく、議論の奥にある、本質的な課題を見極める。ちゃんと考えて話すというのは、相手の言っていることから、その奥に潜む想いを想像して話すこと。
これは学校的思考ではなく社会的思考になる。
5.伝わらないのは、話し方ではなく、考えが足りないせい
「話し方」だけうまくなるな。
話し方では心は動かない。 型に当てはめるだけでは考えたことにならない。「型」はあくまで考えるきっかけ。 言い方には気をつけるべきだが、うまく話せる必要はない。 賢いふりをすればするほど、バカに見えてしまう。 相手に伝わらなければ、話し方が悪かったのではなく、考えが浅かった、と考えるべき。
6.知識は誰かのために使って初めて知性になる
頭にいい人は、”賢い振り”ではなく”知らないふり”をする
相手の話を聞いているとき、簡単にアドバイスはするな、意見を言うな、
とにかく相手に話してもらう。
人間は自分の話をしたい生き物、知識があれば披露したくなる。
だからこちらは知識を披露するのではなく一緒に考え、自分で気づいてもらう。
7.承認欲求を満たす側に回れ
他者の承認欲求をコントロールする
承認欲求をコントロールして、コミュニケーションの強者になるには、
二つの条件がある
1・自信を持つこと
自尊心が低く、自分に自信がない人は、他者をうまく承認することができない。
自尊心が低いと自分で自分を肯定できないため、他者の承認が必要になる。
「他者に承認を要求すること」しかできない人物は「承認欲求を欲する立場」
ですから、ここでは弱い立場といえる。
2・口(自己アピール)ではなく、結果で自分自身をアピールする
他者をほめつつ、自分は「なんでもない人間」という顔をするのが、
コミュニケーション強者の態度であり、知的に慕われる人の態度です。
結果を出した上で、他者に親切にできる人物は徐々に「カリスマ」と呼ばれる。
5つの思考法
客観視の思考法
・話を深くする
・自分の意見と真逆の意見も述べる
・成り立ちを調べる
整理の思考法
・結論から話す
・事実と意見を分ける
傾聴の思考法
・アドバイスではなく整理する
・なにを言うかより、誰が言うか
・ちゃんと聞く(相手が話しているときに自分の話すこと考えない)
質問の思考法
・【万能質問】 質問はたっはたの5種類で成り立つ
(1)導入質問:過去に行った行動についての質問 (2)導入質問:仮定の状況判断に基づく質問 (3)深掘り質問:状況に関する質問 (4) 深掘り質問:行動に関する質問 (5)深掘り質問:成果に関する質問 ・聞きやすい人ではなく、理解している人に聞く ・一度にひとつのことしか聞かない ・目的を知らせる ・具体的に聞く
言語化の思考法
・言語化は挨拶と同じ(習慣にするかどうかだけ)
・ネーミングの力にとことんこだわる ・語彙力を増やす
少し長くなりましたが、この一冊で間違えなく話すときの考え方
聞く時の考え方が変わる、変えれる習慣化は難しいかもしれませんが
意識するだけでもいいです、コミュニケーションを少しずつ学んでいきましょう。
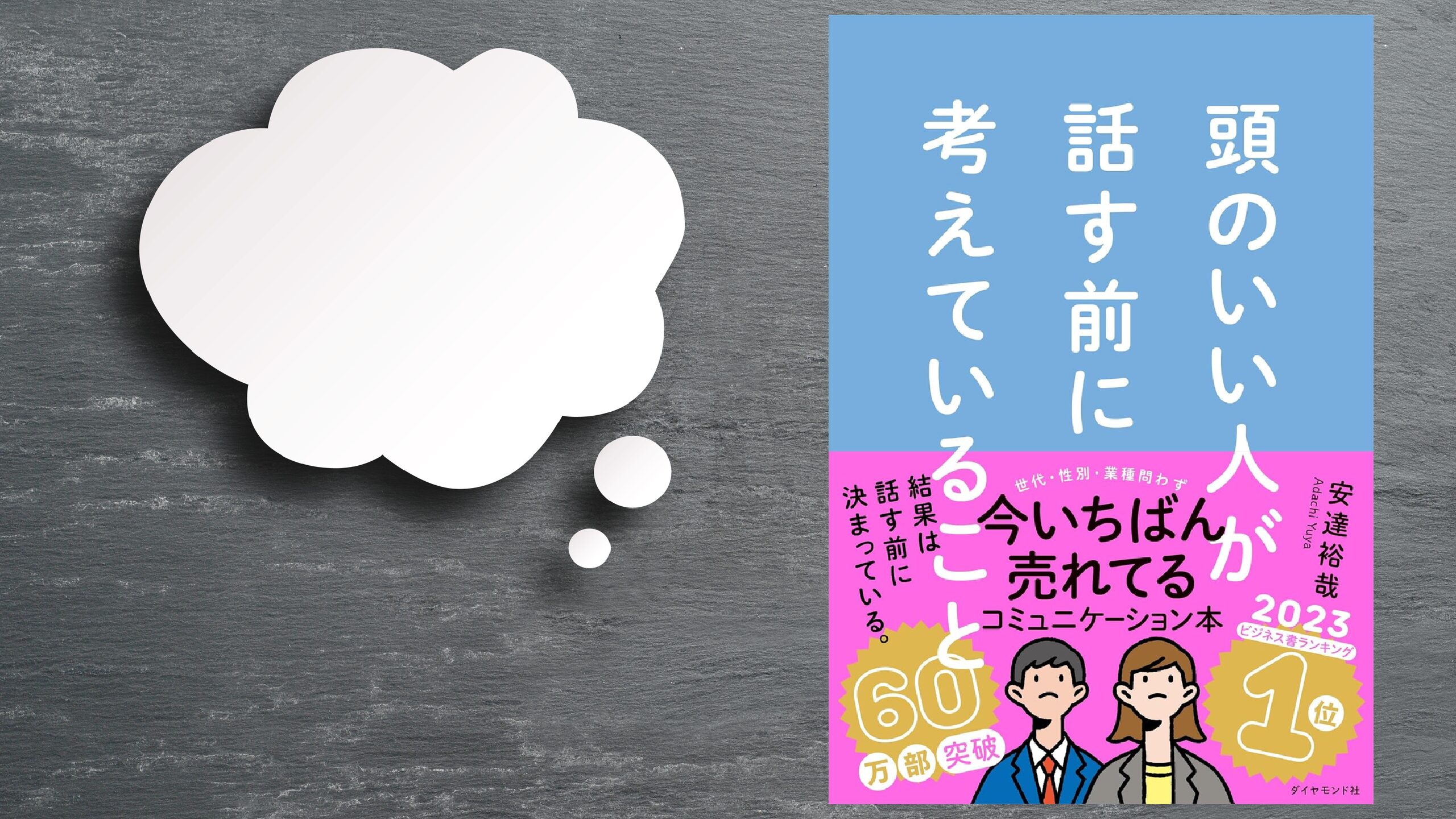




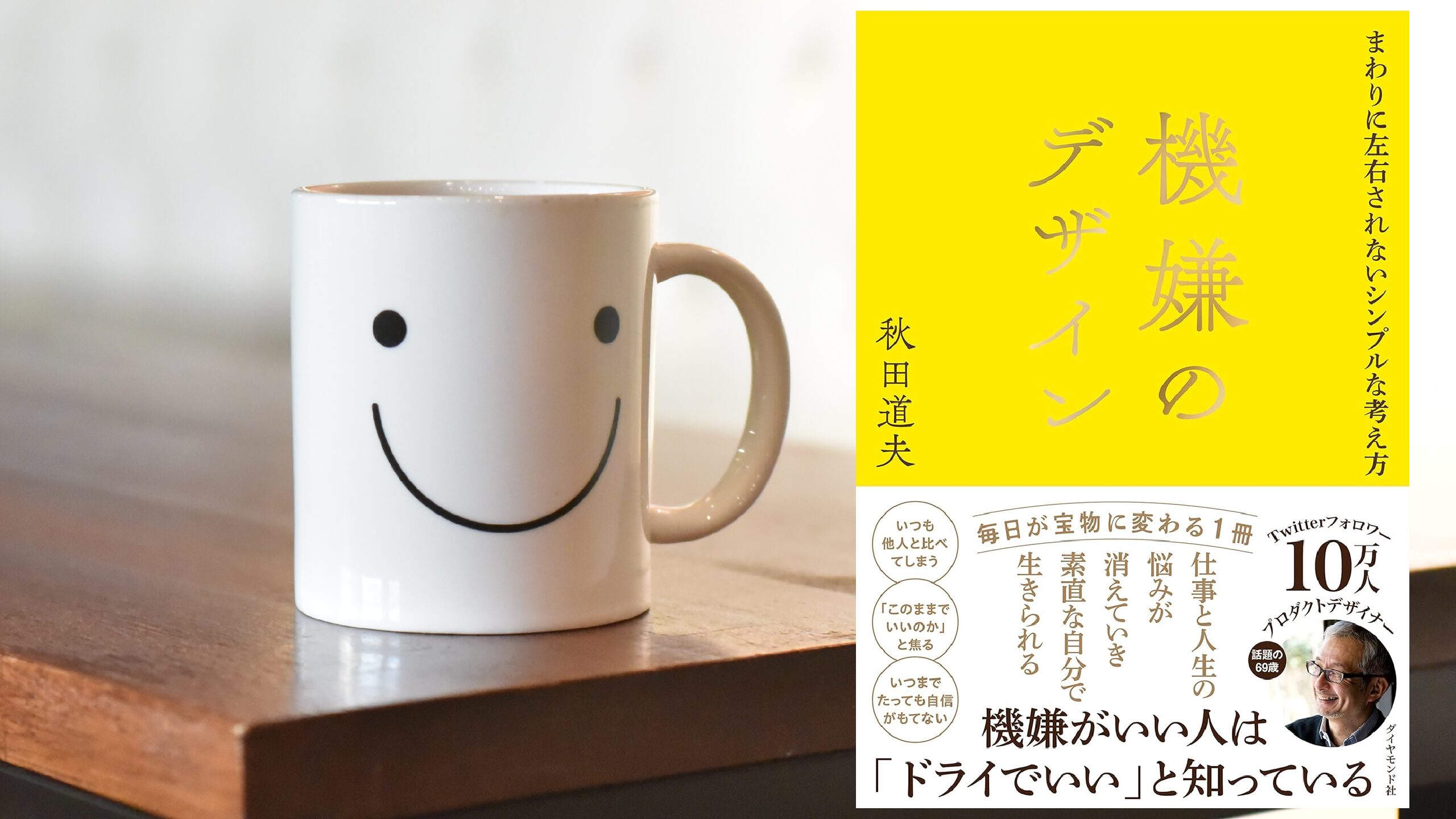

コメント